|
|
subtitle menu |
ジーナ社は、 エルツ山地の村、すぐれた収蔵品を誇るおもちゃ美術館のある〈おもちゃ作りの村〉ザイフェンの隣街ノイハウゼン(Neuhausen)にあります。1850年頃すでに この地方では積木の製造がなされており、フレーベルの理念に基づく玩具作りも始まっていました。19世紀のエルツ地方は、玩具の発祥地として玩具史上大きな意味を持っています。
この地の人々の木製玩具への親しみ、高度の専門技術、品質へのプライドは、今日でも変わることなく守りつづけられています。
ジーナ社の前身であるS.F.フィッシャー(S.F.Fischer)社は1850年頃、木製玩具の製造を始め19世紀末頃にはすでに30種以上の積木や、多種のフレーベル玩具を製造しており、パリ・ロンドン・ミュンヘンで開催された玩具見本市で評価を受けたという記録を残しています。フレーベル玩具を探し歩いていたデュシマ社の創設者クルト・シフラー氏とS.F.フィッシャー社には東西ドイツが二つの国に分離される以前に出会いがあり、お互いに相手を認め合う関係だったと言います。
1989年の東西ドイツの統一は、それまで東ドイツで木製玩具を作っていたS.F.フィッシャー社の存続を脅かすことになりました。急激な資本主義経済への移行に多くの企業が対応しきれず苦戦を強いられた当時、S.F.フィッシャー社も例外ではなく、当時の工場責任者のヴェルナー・ザイドラー(Werner Seidler)氏は企業の存続が不可能な状況に追い込まれ、40名いた従業員を解雇し、工場を閉鎖せざるをえませんでした。しかし彼は、エルツ地方の伝統的な玩具作りを絶やしてはならない、次の世代にも残さなければという情熱をもって、企業の再開を模索し続けていました。
一方、父親のクルト・シフラー氏からエルツ地方には百年以上にわたる良質の木製玩具作りの伝統があり、熟練した有能な職人らがいることを聞いていたデュシマ社のルル・シフラー社長は、壁の崩壊の報にすぐ反応し、父の生前の話にあったS.F.フィッシャー社を探しにザイフェンに向かったのです。1991年デュシマ社の後継者ルル・シフラー女史とザイドラー氏が手を結び合資会社ジーナ社設立にこぎつけた事を父、クルト・シフラー氏の蔭の導きがあったのではないかと思うほど宿命的な出会いだったと女史は回顧しています。社名はルル・シフラーの三女の名前Sinaidaからジーナ(SINA)社としました。
玩具作りの伝統を何とか企業の形で存続させたいと願ったザイドラー氏と、東ドイツの新しい市場への建設的な進出を目指したルル・シフラー女史の出会いから生まれた合資会社ジーナ社は、東西ドイツが別々に歩んだ40年以上の歳月から生じたハード、ソフト両面にわたる多くの問題を一つずつ解決しながら今日も玩具業界の中で、企業理念を守る良心的なメーカーとして頑張っています。
現在では、ザイドラー夫人も運営に加わり社の中心となって活躍しています。
SINA社のホームページ(ドイツ語/英語のみ)はコチラ→http://www.sina-spielzeug.de/
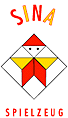 |
|
|||||
|
1. ザイドラー夫妻 |
|||||
![]()
|
東西ドイツの壁の崩壊 |
|||||
|
1991年 |
ジーナ(SINA Spielzeug GmbH)社設立。当時のスタッフは5人。 |
||||
|
1993年 |
ザイドラー夫妻の監督のもと、エルツ山地の伝統的な玩具や、フレーベル理論に基づいた独自の玩具の生産も開始(ジーナモザイク、 ベビーキューブ/NTカタログno.D-24-8,E17-4など)。 |
||||
|
1994年 |
ニュールンベルグ玩具国際見本市に初めて出展。デュシマ社の隣のブースの小さな空間ではあったが、並んだ商品に個性があったため 業界の注目を浴びた。 |
||||
|
1994/95年 |
カールステン・ブラウネ(Karsten Braune)氏のデザインによるジーナブロック(原名 |
||||
|
1997年〜 |
国境を越えた玩具デザイナーによる作品を商品化。 |
||||
|
2000年 |
相沢康夫氏のデザインした積木の商品開発。静岡市にある玩具店 百町森おもちゃ村のスタッフとして活躍する相沢氏は、ネフ社の玩 具デザイナーとしてもその名を知られる存在。今回はネフ氏の仲介で、ジーナ社での商品化が実現。2月のニュールンベルグ見本市で 発表された。 |
![]()
1994年ニュールンベルグの見本市の後、デュシマ社のお誘いを受け、ニキティキのチーム3名はザイフェンのジーナ社を訪ねることになりました。朝早い汽車でケムニッツに向かった3人を、社長のザイドラ−氏が駅まで迎えにきて下さり、駅から車で2時間たらずの道のり、畑や小さい村や林を走りぬけてやっとザイフェンに到着。ジーナ社がデュシマの玩具の生産を請け負ってから、商品の欠陥がいくつか発生していた時期だったので、その原因の究明と対策をデュシマ、ジーナ、ニキティキ3社で現地で話し合うのが訪問の第一目的でした。当時ジーナ社は、ザイフェンのとなり街のノイハウゼンに新しい工場を建てている最中でした。早速引越しを目前に控えたジーナ社・ザイフェン工場を見学。その日作業に携わっていた従業員5、6名、そのうちの2人は、2色モザイクの仕上げ作業中。山と積まれた三角形のパーツを、一つずつ手に取りB品をはぶいて行く仕事です。のどかというか、気の遠くなるような、ゆっくりした時間の流れです。色つけの作業は、ドラムに色と部品を入れて回転させる、従来のデュシマ社の方式がそのまま継承されていました。翌日見本市の事後処理を終え車を飛ばしてルル・シフラーさんが到着。半日をかけての3社会談で、ドイツを出るまでは全く問題がなく正確だった玩具のパーツのサイズが、日本で変化したのは、ジーナ社の木材の乾燥工程の認識に甘さがあったためと判明。(その後、自由経済で生き残っていくことの厳しさの中、ジーナ社はこうした問題を一つずつ解決しながら今日の技術のレベルにこぎつけました。)
会談の後は、ザイドラ−夫妻の案内で、村を回りました。有名なザイフェンの玩具美術館、ジーナ社の建築中の工場、以前から注目していたヴェルナ−さんの玩具工房訪問、そしてザイドラー氏が市長さんに特別の許可をもらってくれて、ヴィザもないのに、小川の小さい橋を渡って、隣国のチェコに入国。小さいレストランでコーヒーを飲んだりと、ちょっと観光気分。生まれてはじめて日本人を見た!と目を丸くされながらご馳走になったコーヒーは、なぜか、ざらざらした口当たりの奇妙なものだった事が懐かしく思い出されます。壁の崩壊後、5年が過ぎた当時でさえザイエフェンは、公衆電話もタクシーもなく、また街灯も少ない村でした。日が暮れて散歩の帰り道がわからなくなった時、案内を乞うため玄関のベルを鳴らしても、窓の奥からの視線は感じられるのに、変な東洋人を警戒して誰も出てきてくれなかったり、どうしても孫に日本人を見せたいので、今夜家にワインを飲みにきて欲しいとホテルを通じて近所の家族に招かれ、行ってみたら、親戚中がカメラを持って日本人を見るために集まっていたりと、3日間のザイフェン滞在は、忙しい日々を過ごす日本人にはタイムスリップしたようなほのぼのしたもので、他のメーカー訪問では味わえない体験となりました。
![]()
|
![]()




